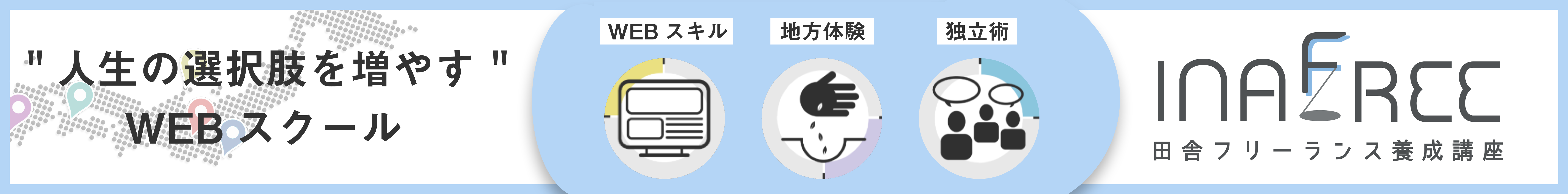皆さんは「先生」という存在に、どのようなイメージを持っているだろうか。真面目。誠実。信頼できる。そんなイメージを持っていますか。
私はそのような「真面目で、素晴らしい、誠実で、信頼できる先生」とやらが、学校不適合な生徒を生み出している場合、がありうるのではないかと思っています。
「学校不適合な子供」は、誰が生み出したのか。
「学校不適合な子供」がいます。いわゆる、問題児と呼ばれる子どもたちです。
授業に集中できず、じっと椅子に座っていられない。喋りだして、授業を妨害してしまう。サボってしまう。友達の輪に馴染めない。学校行事やイベント行事では、抜け出したり、斜に構えて邪魔したり。
さて、ここでひとつ問いたい。
彼らは、学校不適合「だった」のだろうか。それとも、学校不適合と「された」のか?
「障害は、社会の側にある。」
あるLITALICOの社員の方が、こんなことを言っていました。

障害はそこに「ある」ものじゃない。社会の側が作り出しているものだ。
どういうことか説明しましょう。
いまの社会には、「足が不自由な人」という、障害者の方々がいます。
実は足が不自由な人たちは、目が悪い人たちがメガネをかければなんでも見えるのと同じように、車椅子というツールがあれば、本来どこへでもいける人たちです。しかし、社会は「私たち健常者」とやらの目線で構築されてしまっている。そこには、車椅子の人たちの目線がありません。
だから、その社会には隙間があり、段差がある。そしてその隙間や段差に接したとき初めて、彼らは障害を感じる。そこで彼らは、障害者に「される」のです。
社会の側がその視点を持つことができれば、足が不自由な人は、障害者にならなくて済んだはず。すなわち、眼鏡をかけている人たちと同じように、普通の生活を送ることができたはずなんです。
だから、障害は社会の側にある。その環境を変えていこうというのが、LITALICOのミッションなんです。素敵だね。
学校不適合な子どもを生み出す先生
さて。
授業に集中できず、じっと椅子に座っていられない。喋りだして、授業を妨害してしまう。サボってしまう。友達の輪に馴染めない。学校行事やイベント行事では、抜け出したり、斜に構えて邪魔したり。
これはもともと学校で不適合だと定義されていたんでしょうか(暴力や飲酒・喫煙をしてしまえば、それは法律違反なのでまた別ですが…)。それとも誰かが、これは学校に不適合なものに違いないと決めてしまったものなのでしょうか?
そう、私は彼らは、全く問題児じゃないと思ってる。いま先生になっている人って、その大半は学生時代に「まじめな生徒」だった人たちです。そして、学校でいま問題児だとされている生徒は、当時の「まじめな生徒」にとっての「悪役」だった。だから、彼らは「問題児にされてしまった」のではないかと思うのです。
先生という存在は、自分の価値観を基準に、クラスの枠組みの中で見えないルールを設定してしまっている。
こういう行動が正しい、間違い。こういう人が良い、悪い。
結果として、その「先生にとっての間違い」に当てはまってしまった人たちが問題児として定義されてしまっているんです。彼らは、法律や何やらに違反したわけではないでしょう。そしたら、一体彼らは、どんな問題を抱えていると言いたいんでしょうか?
ここで、先生が「彼が問題児というものです」とレッテルをはってしまうことで、生徒自身がそうだよ、俺は問題児だよと内面化してしまう。つまり、そのレッテル貼りは、彼らの「問題」行動を助長します。
そしてひいては、飲酒・喫煙や暴力といった法律違反に至ったり、学校に馴染めずやめてしまったり、といった行動に発展してしまうのではないか。
先生こそ、彼らを抱きしめてやれる存在なのではないか?

先生こそ、そうした社会から弾き出されてしまいそうになる彼らを抱きしめてやれる存在なんじゃないのか。子どもの社会は狭い。そこにいる大人は、親か先生かしかいない場合だって多い。なのに、その貴重な大人の一人が、子どもたちを恣意的に問題児として定義して、あいつらはそういうヤツだからね、といって社会からつま弾きにするようなことが許されるのか。
私が言いたいのは、現在の社会の流れの中で生まれてくる先生という存在が、問題児を生み出しているのではないか、ということ。そして先生たちが、その問題児の存在を増長してしまっているのではないか、ということなんです。
彼らが学校という場から弾き出された時、彼らは一体どこで愛されることができるのでしょうか。
彼らの問題行動はある種の試し行動(=愛情を確認するための行動)でしょう。それは、愛情を求める彼らの叫びでしょう。場合によっては、家庭で不足した愛情を求める、悲痛な叫びなのかもしれない。
では、それを問題行動だといって排除してしまったら。そのとき、彼らはいったい誰に愛してもらえるのか?学校と家庭しか知らないかもしれない彼らを、一体誰が愛してあげられるんでしょうか。
既存の枠組みに執着する、先生という安易な選択をする人々という存在
どうしても先生という存在は真面目だった人が多いんじゃないかと思う。
うまく社会に適合できるがゆえに、小さい頃から、こういうことをすることは悪いやつだ、という連綿と培われてきた常識を、当然のように自分のなかに内面化してしまっている。
もっと言ってしまえば、それらが当然のように内面化されているがゆえに、彼らは「飛び出る杭になってはいけない」という考えを持っていた人たちではないか。つまり、先生とは、あまりこれまでの枠から飛び出ることをしてこなかった人がついている職業なんじゃないか、と僕は思っている。
もちろん、全員が全員そうだと言っているわけじゃない。こんなブログのこんな記事を読んでいるような先生は、面白い(というか変な?)先生に違いない。でも、僕はこうした一部の人を取り上げて、こういう先生もいるだろ!なんて反論はしてほしくない。一部の先生が、そういう先生であればいいわけじゃない。大多数の先生は一体どのような経歴なのか、一体どのような考えで先生になっているのか、そうしたことを改めて考えてほしいんです。
彼らは本当に、子どもたちを幸せにしてやろう、子どもたちの背中を後押してやろうと、そんな存在なんだろうか?安定した仕事だからとか、単に子どもが好きだからとか、そういう理由で先生になっている人のなんと多いことか。
真面目でやってきた彼らには、狭量な視野の狭い彼らには、ぶっとんだやつらを抱きしめてやることができない。受け入れてやることができない。レールを踏み外すということの勇気。レールを踏み外していこうとすることの面白さ、新しい可能性、サイコーっぷり、それを彼らは気づいてやることができないのです。
しかし、先生というのは、そういう人たちばかりだ。それが、いまの日本の現状だ、と僕は思っている。
そんな教育制度の中から、これまでの既存の枠組みを壊して新しいものを作っていこう、面白いことをしていこうと、そういうことができる生徒が、これからの未来を担える大人が、本当に生まれてくるのか?
「まじめな先生にとっての問題児」を、抱きしめてやれる先生を。

さて、昔の内定者同期で、先生になった男がいる。彼との付き合いは浅いけれど、僕は彼の、先生として目指すビジョンを非常に尊敬している。彼に出会えて、本当に良かったと思っている。そして、彼のような先生がたくさん増えてくれたらいいな、と思っている。
彼はサイコーの大学生だった。
大学の授業にはほとんど出ず、大学の屋上でタバコを吸い、酒を飲み、日向ぼっこして日焼けし、海に繰り出しては「女のケツを追いかけ」ていた学生時代だったらしい。ついでに友人と古着屋をはじめ、潰し、また何かしらモテそうなことを見つけては、作り、潰し、そして女のケツを追いかけている。彼は、そんな大学生だった。
そんな彼が、先生になるという。彼は言う。
今の学校は、今の先生は真面目な奴ばかりだから、タバコを吸うやつ、酒を飲むやつ、女の子をナンパするような超おもしれーやつ、そういうやつを誰も救ってやれない。
そんなのはおかしい。俺がそいつらを認めてやる。「お前ら、超おもしろいじゃん。タバコを吸うまでの気づきがあって、あえてお酒を飲もうとするようなバカさがあって、女の子ナンパするような勇気があって、窓を割るような度量があって、お前らみたいな超おもしれーやつら、サイコーじゃないか」って、言ってやりたいんだよね。
俺はそれを聞いて、サイコーだな、と思った。本当は、普通の先生だったら、タバコを吸うやつ、酒を飲むやつ、女の子をナンパするような「超ダメな生徒」というところを、彼は「超おもしれーやつ」と言った。サイコーだなと思った。
そして多分それは、彼しかできないことなんだろうと思う。彼は多分、その生徒たちと一緒にタバコを吸って、一緒に酒を飲んで、お前ら最高だな、って言うんだろう。
それはもしかしたらダメなことなんだろう。でも、そういう、そういう生徒を救ってやれるのは、そういうことをやってきたそいつだけなんだろうと思うんです。
だって俺がいなかったら、誰がそいつらを抱きしめてやれるんだよ。
そう彼は言った。
真面目なやつを褒めてやる先生なんていくらでもいる。だから俺はそうじゃない、落ちこぼれたやつを抱きしめてやれる人間になりたい。
そんな先生が1人でも増えることを願って。